tomiです。
ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
今日は問題30(民法)です。
問題30 留置権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
1 Aは自己所有の建物をBに売却し登記をBに移転した上で、建物の引渡しは代金と引換えにすることを約していたが、Bが代金を支払わないうちにCに当該建物を転売し移転登記を済ませてしまった場合、Aは、Cからの建物引渡請求に対して、 Bに対する代金債権を保全するために留置権を行使することができる。
2 Aが自己所有の建物をBに売却し引き渡したが、登記をBに移転する前にCに二重に売却しCが先に登記を備えた場合、Bは、Cからの建物引渡請求に対して、Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することができる。
3 AがC所有の建物をBに売却し引き渡したが、Cから所有権を取得して移転することができなかった場合、Bは、Cからの建物引渡請求に対して、Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することはできない。
4 Aが自己所有の建物をBに賃貸したが、Bの賃料不払いがあったため賃貸借契約を解除したところ、その後も建物の占有をBが続け、有益費を支出したときは、Bは、Aからの建物明渡請求に対して、Aに対する有益費償還請求権を保全するために留置権を行使することはできない。
5 Aが自己所有の建物をBに賃貸しBからAへ敷金が交付された場合において、賃貸借契約が終了したときは、Bは、Aからの建物明渡請求に対して、A に対する敷金返還請求権を保全するために、同時履行の抗弁権を主張することも留置権を行使することもできない。
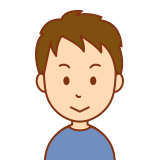
正解は2です。
1 Aは自己所有の建物をBに売却し登記をBに移転した上で、建物の引渡しは代金と引換えにすることを約していたが、Bが代金を支払わないうちにCに当該建物を転売し移転登記を済ませてしまった場合、Aは、Cからの建物引渡請求に対して、 Bに対する代金債権を保全するために留置権を行使することができる。
Aは建物の売却代金を確実に受け取るために、支払いが完了するまでは建物を留置することができます。
そして留置権は物権なので転売されたC対しても行使することができます。(最判昭47.11.16)
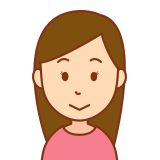
物権は全ての人に対して主張する(絶対的権利)ことができます。
それに対して、債権は特定の人(債務者)に対して主張する(相対的権利)ことができます。
2 妥当でない
2 Aが自己所有の建物をBに売却し引き渡したが、登記をBに移転する前にCに二重に売却しCが先に登記を備えた場合、Bは、Cからの建物引渡請求に対して、Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することができる。
問題から、
ということです。
留置権というのは物(今回は建物)を留置することで債務(損害賠償請求権)の履行を促すことです。
債務者(売主A)ではない者(第二譲受人C)からの建物引渡請求に対して留置権を行使しても、損害賠償請求権の履行を促すことにはなりません。
判例では、不動産の二重売買において第二の買主のため所有権移転登記がされた場合、第一の買主は、第二の買主の明渡請求に対し損害賠償債権をもって留置権を主張することは許されないとされています。(最判昭43.11.21)
3 妥当
3 AがC所有の建物をBに売却し引き渡したが、Cから所有権を取得して移転することができなかった場合、Bは、Cからの建物引渡請求に対して、Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することはできない。
問題から、
債務者(売主A)ではない者(所有者C)からの建物引渡請求に対して留置権を行使しても、損害賠償請求権の履行を促すことにはなりません。
判例では他人の物の売買における買主は、その所有権を移転すべき売主の債務の履行不能による損害賠償債権をもって、所有者の目的物返還請求に対し留置権を主張することは許されないものとされています。(最判昭51.6.17)
4 妥当
4 Aが自己所有の建物をBに賃貸したが、Bの賃料不払いがあったため賃貸借契約を解除したところ、その後も建物の占有をBが続け、有益費を支出したときは、Bは、Aからの建物明渡請求に対して、Aに対する有益費償還請求権を保全するために留置権を行使することはできない。
問題から
5 妥当
5 Aが自己所有の建物をBに賃貸しBからAへ敷金が交付された場合において、賃貸借契約が終了したときは、Bは、Aからの建物明渡請求に対して、A に対する敷金返還請求権を保全するために、同時履行の抗弁権を主張することも留置権を行使することもできない。
判例では賃貸人(A)は、特別の約定のないかぎり賃借人(B)から建物明渡を受けた後に敷金残額を返還すれば足りるものと解すべく、したがって建物明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係にたつものではないと解するのが相当であり、このように賃借人(B)の建物明渡債務が賃貸人(A)の敷金返還債務に対し先履行の関係に立つと解すべき場合にあっては、賃借人(B)は賃貸人(A)に対し敷金返還請求権をもって建物につき留置権を取得する余地はないとされています。(最判昭49.9.2)
以上、今日はここまでです。
最後までご覧いただきましてありがとうございます。



